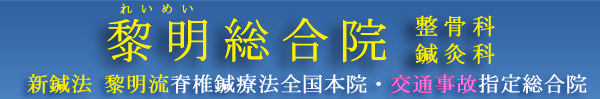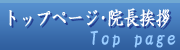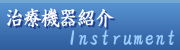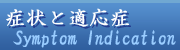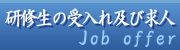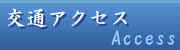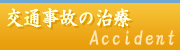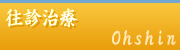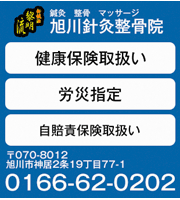著者:黎明総合院
鍼灸院の業種と施術所を開業する時の手続きガイド
- ■2025/07/11 鍼灸院の業種と施術所を開業する時の手続きガイド
-

鍼灸院の開業には、鍼灸師(国家資格)としての準備だけでなく、保健所への届出、施術所としての構造設備基準の理解、提出すべき様式や原本の確認といった、法的・行政的な手続きが密接に関わっています。特に、柔道整復やあん摩マッサージ指圧師など他の医療系施術業務とは異なる分類や業種コードへの理解がないと、届け出段階でつまずくケースもあります。
さらに、日本標準産業分類における「療術業」「医療業」「サービス業」などの分類の違いが業種選択に影響を与えることは、意外と知られていません。開設や施設要件を満たしていないと、保健所に認可されないばかりか、患者からの信頼性を損ねる恐れもあります。
本記事では、実際に施術所の届け出を進める際に注意すべき「設備」「記載内容」「様式」「国家資格の証明」「医療との区分」「届出タイミング」など、開業準備の全体像を明らかにしていきます。
鍼灸院の業種を理解するために知っておくべき基本の考え方
鍼灸に関連する仕事はどのような業種として扱われるのか
鍼灸に携わる仕事がどのような業種に分類されているかは、施術を行う側にとっても、利用者や関係する行政機関にとっても極めて重要な情報です。たとえば、開業を目指す人が提出する開設届や事業計画書には「業種名」の記載が求められますが、その表現を誤ると管轄機関との間で手続きに支障をきたすこともあります。鍼灸は国家資格を必要とする専門的な施術であるため、一見すると医療業の一部のように考えられることがありますが、実際には「療術業」として分類されるのが一般的です。
厚生労働省が示す日本標準産業分類において、鍼灸院は「医療、福祉」の中の「療術業」に含まれています。この分類の中には、はり師やきゅう師が行う施術をはじめ、柔道整復やあん摩マッサージ指圧なども含まれており、共通するのは医師とは異なる立場で体の不調にアプローチする施術を提供しているという点です。ここで注意したいのは、これらの施術は確かに身体への作用をもたらしますが、「医療行為」として法律上の治療に当たるものではなく、代替的な手法として補完的に行われている点です。この違いが、保険の適用範囲や宣伝表現の規制、さらに税務処理にも影響を与えることになります。
鍼灸師として活動する際、個人事業主として開業することも少なくありません。その際に税務署や保健所に提出する開業届や施術所開設届に記載する業種名は、正しく「療術業」とするのが望ましく、曖昧に「治療業」や「医療サービス」などと記すと、内容不備として修正を求められる可能性があります。また、整骨院や整体院、リラクゼーションサロンとの違いが分かりにくくなっている現代では、鍼灸院が正式な国家資格者による施術を行う施設であることを明確に伝えるためにも、業種の定義を正しく理解し、伝える力が問われるのです。
療術業として分類される意味とその背景
鍼灸院が「療術業」という分類に位置づけられる背景には、日本の医療制度の歴史や施術に対する制度的な扱いの変遷が深く関係しています。療術業とは、医師以外の有資格者が身体の不調を改善するために行う施術行為を指し、あん摩マッサージ指圧師や柔道整復師、そして鍼灸師がこのカテゴリーに含まれます。この分類は医師法やあはき法、柔道整復師法といった個別の法律によって制度化されており、特定の国家資格を持つ者に限り、一定の範囲内で業務を行うことが認められています。
そもそも、日本の医療制度における療術という概念は、東洋医学に基づく治療法が長年にわたり民間療法として受け入れられてきた経緯があります。明治以降、西洋医学が公的制度として導入される一方で、鍼灸やあん摩などの伝統的手法も一定のニーズを保ち続けてきました。これらの施術は、医師による医学的治療とは異なるアプローチを取るものであり、その存在を制度的に保証するために、療術業という独自の枠組みが設けられました。
療術業に含まれる施術は、あくまで「医業類似行為」とされ、医療行為とは明確に区別されます。そのため、施術所を開設する際には保健所への届出が必要ですが、病院や診療所とは異なり医療法人化はできないといった制限もあります。この違いは、施術の内容や目的が「治療」ではなく「改善」「回復促進」などに位置づけられることによるものであり、それに伴って広告や宣伝の方法にも一定の規制が設けられています。
たとえば、鍼灸院がチラシやウェブサイトで「治る」「改善する」といった断定的な表現を用いることは、景品表示法や医療広告ガイドラインの観点から問題とされることがあります。これは、療術業における施術が個人差や体質によって効果が異なるという前提のもと、誤認や過大な期待を避ける目的で定められている規制です。施術者が自らの技術を正しく伝え、なおかつ法令を遵守するためには、療術業という業種の意味を深く理解しておく必要があります。
また、療術業に分類されることで得られる制度的なメリットもあります。たとえば、一定の条件下で健康保険が適用される療養費制度や、特定の自治体が施術に対して補助金を出す制度など、国家資格者としての立場を活かした支援が利用できるケースもあります。ただし、これらの制度を活用するには、患者が医師の同意書を取得する必要があるなど、事前の手続きが不可欠であるため、施術者は業種上の制度を正確に把握しておくことが求められます。
鍼灸師の業種と職業との関係を正しく把握する
国家資格をもとに区分される分類の考え方
鍼灸師という職業は、単なる施術者という枠に収まらず、国家資格に裏打ちされた専門的な職種であり、職業分類や業種区分を理解することは法令順守や開業準備、事業運営において極めて重要です。国家資格としての「はり師」「きゅう師」は、厚生労働省によって定められた国家試験に合格することで取得でき、いずれも独立して開業することが可能な医療類似行為の資格です。この国家資格の存在が、鍼灸という施術の社会的信頼性や業務範囲を明確に規定する大きな根拠となっています。
鍼灸師が行う業務は、医師の指示を必要としない「医業類似行為」に該当し、日本標準産業分類上では「療術業」として位置づけられるのが通例です。ここで多くの人が抱える疑問の一つが「療術業とはどのような業種なのか」という点ですが、療術業とは国家資格を持つ鍼灸師やあん摩マッサージ指圧師、柔道整復師などが行う施術を、医療機関とは別に提供する業務全般を指します。
一方で、鍼灸師の施術所は医療法の適用を受けないため、開設にあたり医師のような診療所としての登録義務はないものの、あはき法(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)に基づいて保健所への施術所届出が必要です。この届出の際に求められる様式や設備基準も、職種分類や業種理解を欠いていると不備や再提出の原因になります。
同じ医療類似行為でも、柔道整復師が属する「接骨院」や、あん摩マッサージ指圧師の業務内容とは細部に違いがあり、資格によって施術可能な範囲が明確に線引きされている点も見落としてはなりません。たとえば、鍼灸は「はり」「きゅう」を使って皮膚に直接刺激を与えることが主な施術手法であり、東洋医学に基づいた診断的観点を持って施術が行われるのが特徴です。
業種を区分する際には、提供する施術の種類と、それに必要な資格が何かを明確にすることが重要です。これにより、「整骨院」「接骨院」「整体院」「鍼灸院」など類似した施設名であっても、それぞれが異なる国家資格や職能に支えられていることが分かります。加えて、国家資格の保有者は広告の表示にも制限がかかるため、鍼灸師としての肩書やサービスの表現にも細心の注意が必要です。
近年では美容鍼やスポーツトレーナー分野で鍼灸師の活動領域が広がる中、「何業に該当するのか」「どの分類で保険や税務を考慮すべきか」という視点がより一層重要になっています。特に開業準備を進める鍼灸師にとっては、開設届や施術所管理者要件、施設基準、標榜範囲、届出内容の正確な把握が不可欠であり、国家資格に基づいた職業分類を正しく理解しないままでは、開業後に行政指導や業務停止処分といったリスクも孕みます。
他の施術と混同されがちな違いに注意するポイント
鍼灸院という施術所は、整骨院・接骨院・整体院・リラクゼーションサロンなどと混同されることが多く、実際に患者や利用者から「どこが違うのか」「保険は使えるのか」といった質問が寄せられる場面も少なくありません。こうした混乱が生じる背景には、施設の名称や施術内容が一見似ており、外見上では判断がつかないことが挙げられます。
まず明確にしておくべきなのは、鍼灸師が行う施術は国家資格に基づいて実施されており、東洋医学の理論に基づいたはり・きゅうの技術を用いて体調の改善や痛みの緩和を図るものであるということです。これは整体師やリラクゼーション業とは異なり、施術対象の特定や刺激の方法に医療的な意義が強く含まれています。
鍼灸と整体を混同する例は特に多く、整体が提供する施術は資格不要であるケースが大半です。つまり、整体師には国家資格が不要である一方で、鍼灸師は国家試験に合格しなければ名乗ることも施術することもできません。施術方法も、整体では徒手的に骨格や筋肉の調整を行うのに対し、鍼灸でははりやきゅうによる経絡刺激が中心となります。
整骨院や接骨院は柔道整復師という別の国家資格者が運営する施設であり、主に打撲・捻挫・挫傷などの急性外傷に対して徒手整復を行います。ここでも保険の取り扱いが異なる点に注意が必要で、鍼灸施術は保険適用を受けるために医師の同意書が必要な一方、柔道整復の一部施術は同意書が不要で保険が利用可能です。
リラクゼーションサロンにおいては、「癒やし」や「疲労回復」が主目的であり、施術には医療的な意味が含まれないため保険適用外となります。このように、同じ「体に触れる」施術業でも、それぞれの目的・資格・法律上の立ち位置が明確に異なっており、施術を受ける側も提供する側も、それを誤って理解しているとトラブルに発展する可能性があります。
開業に関わる鍼灸院の業種上の届け出と手続きの視点
保健所や関係機関に提出する書類の扱いについて
鍼灸院を開業する際には、保健所などへの届け出が法律で義務付けられており、施術所として認められるための重要な手続きです。特に療術業に該当する場合、国家資格を持つ施術者が適切に対応する必要があります。
代表的な書類は「施術所開設届」で、所在地や開設者名、施術内容、設備などを記入します。保健所ごとに様式が異なるため、指定に従って記入しましょう。管理者が開設者と異なる場合は、その届出も必要です。また、国家資格証の写しも提出し、資格が複数ある場合はすべてを添付します。原本の提示を求められることもあるため、持参すると安心です。
施設の構造についても、保健所が定める一定の基準を満たしている必要があります。たとえば、施術室の面積、換気の状況、プライバシーの確保、衛生設備の整備などが確認されます。施術室をカーテンで仕切っただけでは基準を満たさない可能性があるため、壁や扉によって施術空間を明確に区切ることが望ましいです。
これらの書類を準備する際には、記載ミスや記入漏れによって再提出を求められることがあります。例えば、設備図に施術台の配置が明記されていなかったり、施術機器の使用目的が曖昧だったりすると、開業スケジュールに影響を及ぼすことがあります。そのため、書類の作成前に保健所へ事前相談を行うと安心です。
なお、必要書類や手続きの詳細は自治体によって若干異なる場合があります。市区町村ごとに対応が異なることもありますので、開業を予定している地域の保健所に直接問い合わせて確認することが大切です。多くの自治体では、開業予定者に対して事前相談や書類チェックのサービスを提供しており、制度を利用することで手続きがスムーズに進みます。
施術所として扱われるために必要な環境整備
鍼灸院を正式な施術所として開業するためには、法令で定められた環境整備を行う必要があります。これは、利用者にとって安全で清潔な施術環境を提供するためだけでなく、施術者の専門性や信頼性を社会に示すためにも欠かせない要件です。国家資格を保有している施術者であっても、施設面の不備があると、開業許可が下りないことがあります。
施術室には十分な広さと構造上の独立性が求められます。たとえば、自宅の一部を施術室として使う場合でも、生活空間と明確に分離されていなければなりません。患者のプライバシーを守れる構造か、換気・採光・防音などの面で問題がないかなど、事前のチェックが重要です。保健所の担当者が実地で確認することもあるため、基準に沿った整備を行う必要があります。
待合室や洗面設備などの付帯設備も整えることが望ましいとされています。手洗いや消毒がスムーズに行えるように、洗面台やアルコール消毒液の設置、器具の滅菌設備の整備も必要です。使い捨て鍼の使用が推奨されており、再利用する場合は、適切な滅菌処理を実施する体制が求められます。
施術に使用する器具の保管や管理にも注意が必要です。鍼や灸、温熱機器、ベッドなどの使用状況や衛生状態が適切かどうか、開業後も継続して記録・管理する仕組みを整えることが、施術者としての信頼につながります。また、施術者が複数いる場合は、器具や施術スペースの共有ルールを明確にしておくことも重要です。
建物の構造そのものが開業条件に影響することもあります。天井の高さ、出入口の幅、バリアフリー対応の有無など、基準に達していない場合は改装が必要になることもあります。したがって、物件を選ぶ段階から、開業地の保健所に相談して条件を確認しておくとスムーズです。
鍼灸院の業種における環境整備は、単に形式を整えるだけではなく、施術の品質や患者の安心感に直結する重要な要素です。設備や構造がしっかり整っていることは、療術業に分類される鍼灸院にとって、法令遵守の証であり、患者からの信頼を築く基礎でもあります。届け出と並行して、物理的な環境や日常の運営体制についても万全に整えることで、安定した施術所経営が可能になります。
まとめ
鍼灸院の開業には、施術者としての国家資格取得だけでなく、行政上の手続きや業種分類の理解が求められます。中でも保健所への届出は、鍼灸院が医療類似行為を行う施術所として正式に認可されるために避けて通れない重要なステップです。施設基準や構造要件を満たしていなければ、開設自体が認められず、計画が頓挫することもあります。
特に日本標準産業分類においては、「療術業」や「医療業」「サービス業」など、施術内容や資格の違いによって分類が異なるため、適切な業種コードの選定が必要です。これは保健所での提出様式や手続きにも関わり、間違った分類で届出を行うと再提出を求められる可能性もあります。
施設整備の面でも、単にベッドと機器がそろっていればよいというわけではありません。施術者が安全に施術を行える空間の確保や、患者が安心して施術を受けられる動線、衛生設備なども含め、細かい基準を満たす必要があります。これらは厚生労働省が示す基準や各自治体の判断に準じて整備されるべきで、事前の情報収集と準備が成功の鍵を握ります。
施術の技術や経験はもちろん大切ですが、開業を円滑に進めるには、届け出や業種分類といった行政的な視点を持つことが不可欠です。時間や費用、手間を無駄にしないためにも、施術所としての立ち位置を正しく理解し、制度に即した準備を進めていきましょう。鍼灸院として長く信頼される存在となるためには、こうした土台作りこそが最初の一歩です。
よくある質問
Q. 鍼灸院の業種分類で「療術業」に該当する意味とはどういうものですか
A. 日本標準産業分類では、鍼灸院は療術業として扱われます。これは、医師の資格を持たずに東洋医学に基づく施術を行う業種であり、医療業とは明確に異なる位置づけです。鍼灸、あん摩、マッサージ、指圧などの国家資格を保有していれば療術業に分類され、業務内容に応じた制度的な支援や申請様式が適用されるのが特徴です。
Q. 鍼灸師が整体や整骨とどのように違うのか混同されやすいのはなぜですか
A. 鍼灸師は国家資格に基づいて施術を行う職種であり、柔道整復師や整体師とは資格の種別も業務範囲も異なります。しかし、患者の症状に応じて行う施術が似ていることや、施術所の外観が近しいことから混同されやすいのが現状です。特に整体は資格制度が存在しないため、施術者の専門性に差があり、国家資格のある鍼灸師との区別は、患者自身が理解を深める必要があります。
院概要
院名・・・黎明総合院
所在地・・・〒077-0835 北海道札幌市東区北35条東15丁目1−17
電話番号・・・011-704-7171
新着一覧
- ■2026/01/05 1月の祝日は平常通りの診療です
- ■2025/12/04 12月の診療案内
- ■2025/11/04 11月診療時間のお知らせ
- ■2025/09/26 10月祝日は休診します
- ■2025/08/29 元町駅で鍼灸院の失敗しない選択